こんにちは、くっかばらです。このブログでは、自分の経験からおすすめの山などを紹介しています。今回は、お鉢巡りや火口の眺めが楽しめる山を紹介します。全て関東から前泊または日帰りで行ける山で、私が実際に行った山です。
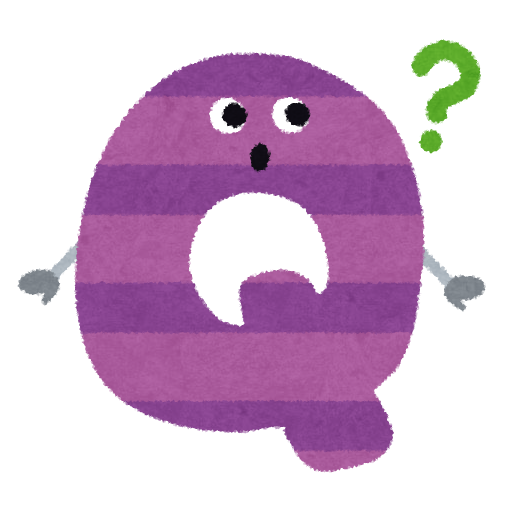
お鉢巡りが楽しめる山に行きたいな。注意することはある?
大前提として活火山に登るときは、火山活動や立入規制について情報収集をしたうえで、例え警戒レベルが1であっても万が一に備えた行動を取りたいです。正直、私は以前はあまり意識していなかったのですが、やはり2016年の御嶽山噴火は衝撃で、その後の行動は少し変わったように思います。といっても、情報収集をして、万が一噴火した場合の行動を考えるだけなのですが・・・。

活火山の定義は近年少し変わり、1万年以内に噴火活動があり現在活発な噴気活動のある山、ということです(気象庁HP)。
情報収集は気象庁のサイト中心に見ています。地図に活火山が表示されているので、クリックすると現在の状況や過去の火山活動が確認できて便利です。
噴火して一番怖いのは噴石に当たること、そして火山灰ですね。避難小屋や物陰があれば隠れて、最悪はザックで頭部分を守る。タオル(濡れタオルであればベスト)などで口を覆う。コンタクトレンズは出来れば外してメガネ。噴火が少し落ち着いたら退避。など色々な対策がネットで紹介されています。特に活火山へ行く時はヘルメットを持っていくようにしたいですし、そういう人が増えているように思います。

御嶽山の上部では立入OKなルートであっても、地元自治体によりヘルメット着用が求められています。
たまたま先日、火口へ降りて撮影するという内容のアドベンチャー番組を見ていて、その時に「もし噴火音を聞いたら上を見て横に逃げる。絶対に走り出してはいけない」と言っていました。落ち着いて行動したいですね(自信がないですが・・・)。
少し重めの話題から始めてしまいましたが、お鉢巡りや火口付近を歩くのは、雄大で山のパワーを直に感じてとても楽しいです。
① 富士山

富士山のお鉢は思っていたよりも小さく、土砂採取場のような趣きなのが意外でした。どの登山口から入っても頂上でお鉢巡りルートに組み込まれます。できれば時計回りで回るほうがよいと思います。剣ヶ峰(写真の右奥)の手前がものすごい急登で、時計回りで登るほうがまだ楽だからです。

私はルート的に反時計回りしたため、かなり苦労して下りました。
富士山に行ったら絶対歩きたかったのが、宝永火口です。このために、登りは吉田ルートから入ったのですが、下りはプリンスルート(御殿場口へ向かって下り、走り六合で宝永火口を横切って富士宮口へ下山するルート)を取りました。御殿場口へのルートは小屋も少なく、大量の砂で独特の歩きが必要になります(スパッツも必須!)。それらの苦労を差し引いても、火口内を歩くという非現実さ、一面砂の火星のような眺め、何もかも素晴らしかったので、ぜひ行ってみてほしいです。

富士山登山の記事を書いていますので、よろしければどうぞ↓

② 安達太良山


福島の名峰、安達太良山。山頂も楽しいですが、少し足を伸ばして牛の背から鉄山や船明神山へ向かうと、沼ノ平の壮大な爆裂火口の眺めを楽しめます。
昔は火口内を歩けたようですが、現在は立入禁止になっています。以前には有毒ガスによる死亡事故もあり、絶対に降りていかないようにしましょう。
私はロープウェイは使わずに奥岳登山口から入り、くろがね小屋経由で山頂へ向かい、その後は牛の首から鉄山避難小屋を廻って沼尻温泉へ下山するルートを取りました。途中に湯の花採取場があるのですが、白濁の温泉がこんこんと噴出していて、活火山のパワーを感じました。


西側へのお鉢巡りは胎内岩などアドベンチャーな歩きができますが、日帰りは厳しくなります。
③ 磐梯山(会津)


磐梯山は、表磐梯と裏磐梯で景観が全く異なるのが面白い山です。表磐梯(猪苗代湖側)から見ると普通の山なのですが、裏磐梯(桧原湖側)は山体がふっとんでいるのがよくわかります。これは明治時代の大規模噴火で山体崩壊が生じたため。火災泥流が川をせき止めて桧原湖や五色沼が出来たと言われています。500人近い犠牲者が出たとても痛ましい噴火でした。
登山口は表磐梯に3つ、裏磐梯にも3つあります。私は表磐梯の猪苗代スキー場から入り、沼ノ平を経由して弘法清水から山頂へ、下山は裏磐梯スキー場へ下りました。行程が長い上に累積標高も大きくてかなり疲れましたが、このルートは磐梯山の良いところを全部取りできるルートだと思います。表磐梯からは急登ながらもよく整備され歩きやすく、振り返れば猪苗代湖の眺望がきれいでした。下山のときは大規模噴火でできた火口壁を近くにみながら歩け、銅沼がきれいです。


登山地図にはないですが、櫛ヶ峰へ歩いていく道がついていて登っている人もいました。


④ 硫黄岳(八ヶ岳)


八ヶ岳の硫黄岳では、山頂の片側(夏沢峠側)が深く落ち込んでいる迫力の山体を見ることができます。山頂付近は平らなので、突然の切れ落ち方に驚いたことを覚えています。
「爆裂火口」と呼ばれていますが、火山活動によるのか山体崩落によるのか、諸説あるようです。八ヶ岳は1万年以上前に火山活動で形成されたということですが、硫黄岳は現在は活火山に数えられておらず、お隣の横岳が活火山です。
硫黄岳は東西南北から登ることができます。私は夏は赤岳鉱泉側、冬は夏沢峠から登りました。初夏(7月頃)にはコマクサの群生が可憐で、シャクナゲもたくさん咲いていました。


⑤ 那須岳(茶臼岳)


那須岳は那須三山(茶臼岳・朝日岳・三本槍岳)の総称として呼ばれることもありますが、狭義には主峰の茶臼岳を差します。茶臼岳山頂ではぐるりとお鉢巡りができます。ただ、安達太良山のような壮大な眺めというわけではなく、どちらかというと富士山のお鉢巡りのように、真っ黒な土が見えるだけです。とはいえ、登山道付近からも白い湯気がしゅうしゅう上がり、強めな硫黄のにおいがして活火山のパワーを感じるには十分。
那須ロープウェイを使えば楽に登頂できるので、初心者さんにも向いています。那須三山の縦走プランにすればロングルートとなり健脚向けです。東京からのアクセスも良く、ふもとでは白濁・硫黄臭の湯本温泉に浸かるのが楽しみ。秋は姥ケ平の紅葉が有名です。
那須三山縦走の記事を書いていますので、よろしければどうぞ↓



⑥ 浅間山(前掛山)


関東住みにとっては一番ニュースで聞く活火山です。歴史上では天明の大飢饉の原因となった大噴火を始め大規模な噴火が記録されており、また過去数年の間にも小規模な水蒸気噴火を繰り返している山です。
浅間山の火口付近は長い間立入禁止になっており、前掛山までしか登れません。浅間山は外輪山が2重になったような構造になっていて、浅間山のまわりに前掛山があり、そのまわりを黒斑山を始めとするカルデラ外輪山が取り囲んでいます。浅間山はしばらく噴火危険レベル2で外側の外輪山までしか立ち入れませんでしたが、現在はレベル1で前掛山まで登れます。


とはいえかなり緊張して登りました。ヘルメットをしている人は多め。中にはガスマスクのようなのをしている人も。分岐には「自己責任」の警告看板が。
個人的には10月下旬のカラマツの紅葉が素敵だと思います。浅間山の黒い山肌にカラマツのゴールドが映えてとてもきれいでした。私は車坂峠から入り黒斑山、Jバンド、前掛山とまわって、草すべりを登り返して下山しました。日帰りで間に合う時間に帰ってこれましたが、結構なハードな歩きになりました。
前掛山登山の記事を書いていますので、よろしければどうぞ↓






コメント